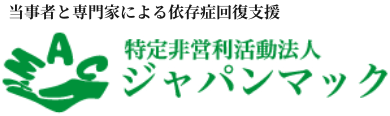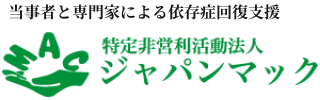11月24日、大阪市の常光寺で「バーキース」主催の第2回「アルコール依存に関する勉強会」が開催されました。テーマは「ヒトと酒」。2人の専門家がゲストで招かれ、酒と人間の関係について深く掘り下げた話が展開されました。
(トップの画像は会場の常光寺)
11月24日、大阪市にある常光寺で、国産ウイスキー専門店「バーキース」(大阪市淀川区)主催の第2回「アルコール依存に関する勉強会」が開催されました。この勉強会は、お酒を愛しつつも悩みを抱える飲食業者たちとともに、アルコールの負の側面に焦点を当て、その特性を正しく理解し、より健康で楽しい飲酒生活を送るための知識や視点を提供することを目指したものです。
悲劇を繰り返さないための勉強会
バーキースのマスターである山本照彦氏は「バーテンダーとしてのキャリアの中で、アルコールが原因で命を落とした後輩や、アルコール依存症に苦しみ、さらにコロナに感染して植物状態となった友人を見てきた」と語ります。この経験から、こうした悲劇を繰り返さないために勉強会を企画したそうです。今回は、歴史学を専門とする古谷大輔先生と脳神経外科専門医の宮崎晃一先生をゲストに迎え、テーマ「ヒトと酒」を掘り下げた話が展開されました。
人と依存
古谷大輔先生(大阪大学大学院人文研究科教授)は、アルコールやカフェインといった嗜好品が歴史や文化の中でどのように社会に根付いてきたかを考察しました。特に、アルコール依存の本質が社会生活における心理的な苦痛や絶望感と深く結びついている点に言及。また、アルコール消費に対する規制の有無やその厳しさが、依存症の広がりに大きく影響することを解説しました。アルコールやカフェインそのものが問題なのではなく、考えるべきは「依存を生み出す社会の姿」と指摘しています。
人と酒
宮崎晃一先生 (互恵会大阪回生病院 脳神経外科部長 医学博士)はアルコール依存症のスクリーニングテスト「AUDIT」を参加者に実施、アルコールとの関わりを見直す機会を提供しました。また、脳神経外科臨床の最前線で診療を行う医師ならではの視点から、お酒が要因となり繰り返し救急搬送される患者の状況や、それに直面する中で抱いた想いが語られ、その内容は非常に説得力がありました。
「稀有な取り組みへの敬意」
今回の勉強会に参加したジャパンマック事務局長の森啓介氏は、嗜好品が個人の問題にとどまらず、社会全体で捉えるべき課題であることを強く認識したと語ります。
「アルコールやカフェインといった嗜好品が、ただの個人の嗜好ではなく、社会全体の課題として捉えられるべきものであることを強く認識しました。特に、古谷先生の講演では、歴史や文化の中で嗜好品がどのように広がり、そして依存症がどのように生まれてきたかが鮮明に語られ、非常に考えさせられる内容でした」
また、森氏は主催者であるバーキースの山本氏の取り組みに対し、敬意と共感を抱いたと述べました。
「飲食業に携わる方々が、自らの業界の課題を認識し、こうして積極的に解決に向けた場を提供されることは本当に稀有な例です。依存症という病気に対する不寛容さや偏見がいまだ強い社会の中で、このような勉強会が多くの人にとって気づきのきっかけとなることを願っています」
寄付のご報告
本勉強会の参加費から経費を差し引いた金額を、ジャパンマックに寄付いただける予定です。主催者および参加者の皆様に心より感謝申し上げます
相談窓口のご案内
依存症に関するご相談は、ジャパンマックのウェブサイトの問い合わせフォームやお電話にて承っております。依存症でお悩みの方やご家族の方は、どうぞお気軽にご連絡ください。
- 電話でのお問い合わせ:03-3916-7878
- 相談フォーム:ジャパンマック 依存症相談ページ