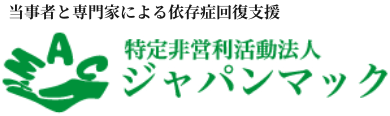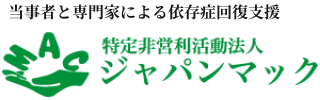大切なはずの家族との時間、仕事への責任、そして自分自身の健康。依存症は、そうした人生の基盤を少しずつ、しかし確実に後回しにさせてしまう病気です。問題は単純な「使い過ぎ」ではなく、脳の機能が変化し、物事の「優先順位づけ」が正常にできなくなることにあります。本人だけでなく、周りの人々をも巻き込む依存症の本当の問題とは何か。厚生労働省の情報を基に解説します。
依存症が本当に蝕むもの
「お酒の飲み過ぎ」
「ギャンブルのやり過ぎ」
そう聞くと、多くの人が「お金を使いすぎる」「体を壊す」といった問題を思い浮かべるかもしれません。もちろん、それらも深刻な問題です。しかし、依存症の本当の怖さ、そして最も深刻な問題は、私たちの人生の土台そのものを蝕んでいく点にあります。
今回は、厚生労働省の情報も参考にしながら、「依存症の本当の問題とは何か」について、一緒に考えていきたいと思います。
深刻な問題は「人生の優先順位が乗っ取られる」ことです。依存症になると、脳の中で特定の物質や行為が「何よりも大切なもの」として認識されるようになります。厚生労働省のサイトではこれを「脳の状態が変化し、自分で自分の欲求をコントロールできなくなってしまう状態」と説明しています。
これは、意志の弱さや性格の問題ではありません。脳という、私たちの司令塔が病気によってハイジャックされてしまうような状態です。
乗っ取られる優先順位
その結果、人生における「優先順位」が大きく変わり始めます。
「大切な家族との約束」よりも、「今すぐの一杯のお酒」
「明日の大事な仕事」よりも、「あと一勝負のギャンブル」
「将来の自分の健康」よりも、「一瞬の快感をもたらす薬物」
本来、私たちが大切にしていたはずのものが、後回しにされてしまうのです。
問題は本人だけにとどまりません。そして、この「優先順位」は、本人だけの問題では収まりません。むしろ、最も近くにいるご家族や周りの人々を巻き込み、その生活をも蝕んでいきます。厚生労働省のサイトにもあるように、依存症の症状として「家族に嘘をついたり、借金をしたり、隠したりする行為」は、決して珍しいことではありません。嘘をつかれた家族は心を傷つけられ、人間関係は壊れていきます。
本人が作った借金を肩代わりをすると、経済的にも精神的にも追い詰められていきます。なんとか助けたい、隠してあげたいという愛情が、結果的に本人の問題と向き合う機会を奪い、問題をさらに深刻化させてしまう「イネイブリング」という皮肉な状況に陥ることもあります。
本人の健康や社会生活が損なわれると同時に、家族もまた、笑顔や安らかな眠り、穏やかな日常といった「当たり前の生活」を失ってしまうのです。
では、どうすればいいのでしょうか?
依存症は、回復が可能な病気です。専門の医療機関や相談機関、そして私たちジャパンマックのような自助グループ(同じ経験を持つ仲間の集まり)の助けが大切になります。
■参考文献
出典:依存症についてもっと知りたい方へ (2025年07月28日閲覧)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000149274.html
依存症とジャパンマックの回復支援活動
アルコールなどの依存症は、自分の意思とは関係なく依存が形成される病気です。習慣的な要因によるもので、誰にでも陥るリスクがあります。 1978年に設立されたジャパンマックは、日本で初めて12ステッププログラムを導入した依存症支援施設であり、依存症に苦しむ多くの人々の回復をサポートしています。長年の経験をもとに依存しない生活を送れるよう支援し、社会復帰を目指すためのプログラムを提供しています。
相談窓口のご案内
依存症に関するご相談は、ジャパンマックのウェブサイトの問い合わせフォームやお電話にて承っております。依存症でお悩みの方やご家族の方は、どうぞお気軽にご連絡ください。
-
電話でのお問い合わせ:03-3916-7878
相談フォーム:ジャパンマック 依存症相談ページ